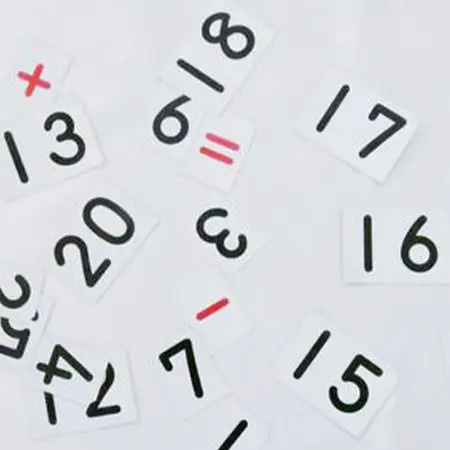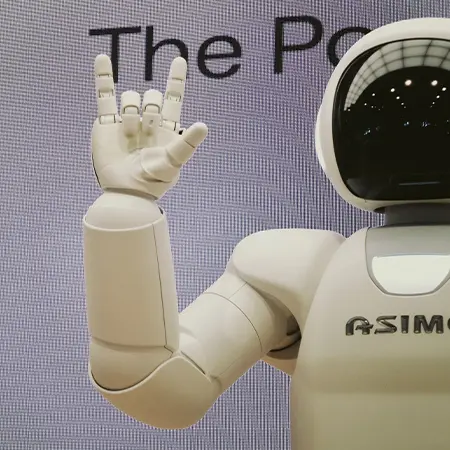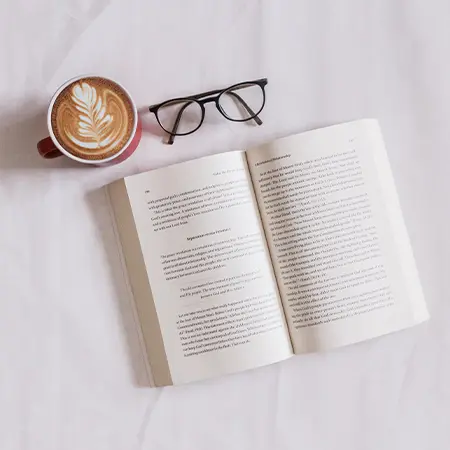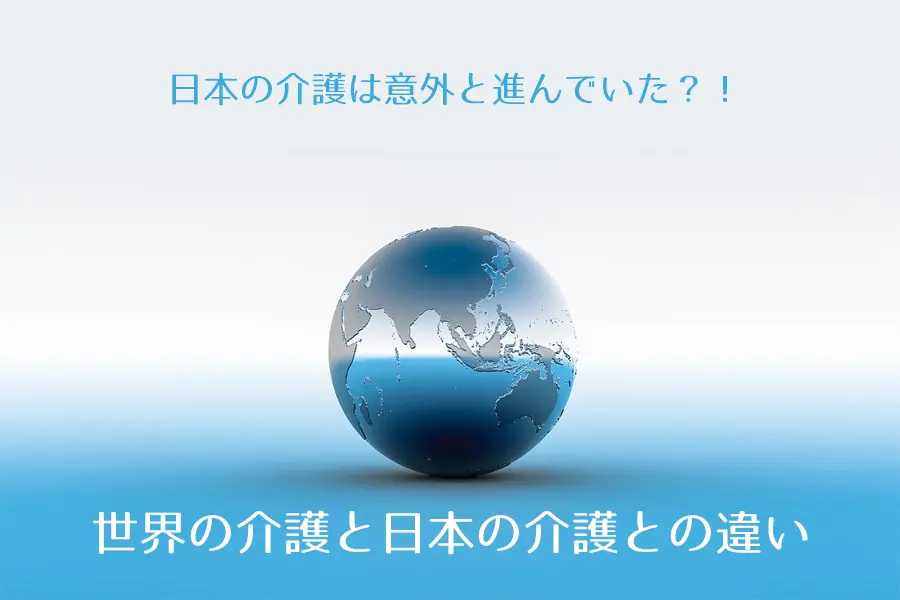令和7(2025)年には、団塊の世代(いわゆるベビーブーム世代)がすべて75歳以上となり、後期高齢者に到達します。これにより、高齢者人口は約3,600万人に達すると見込まれており、日本の総人口に占める割合もおよそ3人に1人を占める計算になります。
これまでの高齢化の課題は「スピード(進行の早さ)」でしたが、現在では「規模(高齢者数の多さ)」が深刻な社会的課題となりつつあります。
総務省の発表によると、令和6(2024)年時点で日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合はおよそ29.1%に達し、過去最高を更新し続けております。つまり、日本人のおよそ3.4人に1人が高齢者という計算になります。超高齢社会の進行はますます顕著になっており、介護や医療、地域社会の在り方が大きな課題となっております。
下の表は、世界の高齢化率(高齢者人口比率) および、合計特殊出生率の国際ランキングです。

医療の発達などで平均寿命が伸びたことから、高齢化は世界各地で起きています。
超高齢社会がもたらす課題として、総務省では働き手の主力とされる15歳以上65歳未満の「生産年齢人口」の減少や、介護負担の増大などをあげていますが、これは「働きながら家族の介護をする人」が増加することも意味しています。
日本では現在、介護職に従事している人は約220万人にのぼります(2023年度時点)。しかし、高齢者人口の増加に伴い、2040年にはおよそ280万人の介護人材が必要になると見込まれており、慢性的な人手不足が懸念されております。
介護職の処遇改善やICT導入による業務効率化など、労働環境の見直しが進められている一方で、他の国々ではどのような介護支援体制が整えられているのでしょうか?
✓介護にかかる費用の1割の自己負担で済む
✓サービス事業所が多数あるので、自分が気に入ったところを選択できる
✓介護保険の場合は民事上の損害賠償請求までできる
✓福祉ミックスや、ボランティアといったNPO雇用者数が多い
✓不法外国人労働者が問題となっている
✓介護施設の料金が高い
✓介護保険は重度要介護者向けが中心
✓保険給付額が限られており、自宅での介護が中心
✓在宅介護が主流であり、老人が安心して介護サービスを受けられるような環境が整っている
✓作業療法や理学療法により、自立した生活を送れるようなサポートがある
✓住宅改修やリフォームの費用補助がある
✓高齢者用の施設が多数あり、国が経営しているものから民間のものまで幅広くある
✓施設に入居する際には支払い能力の無い人に対して手当が与えられることがある
✓介護職の国家資格として社会生活介護士と医療系介護士がある
✓自宅で介護を受けている人に対するサービスが充実している
✓高齢者が住宅で満足できる生活を送れることを国や市が保証している
✓高齢化対策の先進モデル国として注目されている
✓重度の介護者に限定されるが、国から介護給付を受けられる
✓在宅ケアをサポートするためのサービスが充実している
✓施設での介護ケアはそれほど重視されていない
✓多くの介護施設に運動・リハビリ設備が併設
✓要介護度の低い人への在宅支援がある
✓移民を活用した介護人材の確保が進んでいる
✓多段階の介護ステージをひとつの施設で補うケアモデル
✓介護関連職の給与水準が比較的高い
✓介護・リハビリの保障は限定的で、民間保険依存が強い
海外における介護サービスは主に重度者を対象としたサービスです。
日本は、軽度者向けのサービス制度もあり、介護サービスは、諸外国に比べ、充実していると言えるでしょう。

日本の介護サービスや制度は、世界的に見ても高い評価を受けております。しかし、国内における利用者や介護従事者の満足度は必ずしも高いとは言えず、今後、現場の疲弊やサービスの質の低下につながる懸念もあります。
介護分野には多くの課題が残されておりますが、雇用環境の改善や職場の魅力づくり、施設のイメージ改革といった取り組みが求められております。
誰もが安心して介護に関わり、高齢者が尊厳を持って暮らし続けられる社会の実現に向け、今こそ働きやすい環境づくりと制度の進化が不可欠です。
スポンサーリンク